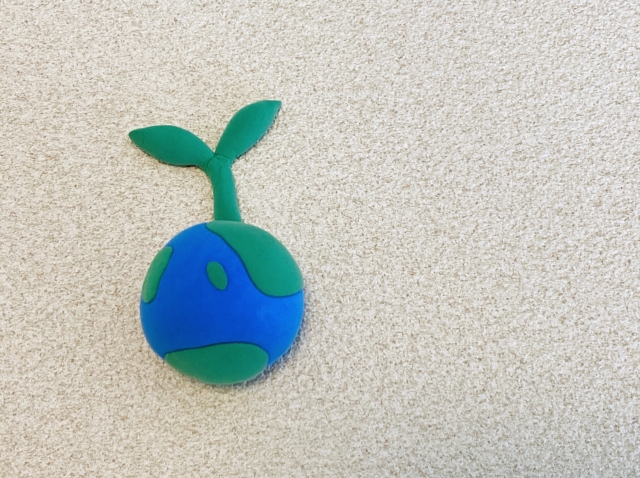産業廃棄物処理施設技術管理者講習の概要
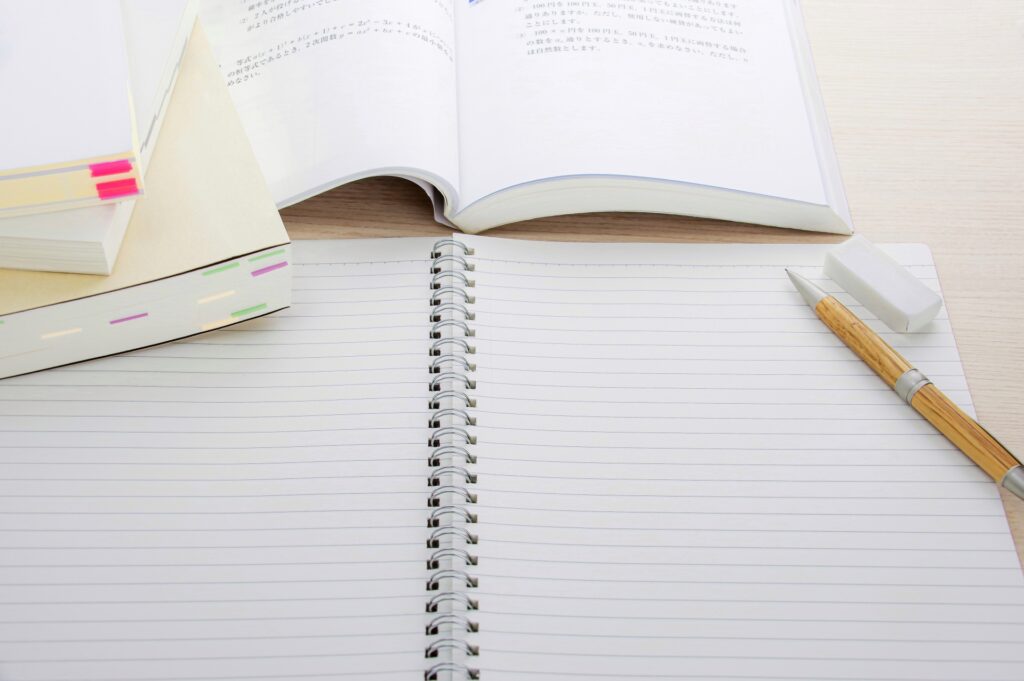
この講習は、産業廃棄物処理法を遵守し、適切な廃棄物処理を実施するための管理者を育成することを目的としています。
処理施設の運営には、環境への影響を考慮し、適正な処理方法を実施するための知識が不可欠です。また、産業廃棄物処理施設を運営するためには、適切な処理技術や法的知識を持つ管理者を配置することが義務付けられています。
産業廃棄物処分業の許可を申請する際にも行政に対してきちんとした知識や技術をもつ管理者が居ることを証明することが必要です。
そこで「一般社団法人 日本環境衛生センター」という組織が開催している「産業廃棄物処理施設技術管理者講習」という講習を修了し、試験に合格すると発行される認定証が必要になってきます。
また、この「産業廃棄物処理施設技術管理者講習」はいくつかのコースが用意されており、設置する施設が導入しようとしている処理内容により受講が必要なコースが異なってきます。これは適正な処理を行うための知識と技能を学ぶ重要な研修です。
本記事では、この講習の概要や受講資格、講習内容、取得後の実務への影響について解説します。
技術管理者講習(中間処理施設コース)とは?
このコースは液体に関係する廃棄物を処分する施設へ従事する方を想定したコース内容になっています。
液体に関する廃棄物とは例えば自動車整備工場から出るエンジンオイルなどをはじめとした「廃油」と呼ばれるものや、各種化学工場などで排出されるアルカリ性の液体や酸性の液体(廃棄物の世界では「廃酸」「廃アルカリ」などと呼ばれる。)などがあげられます。
これらの廃棄物を回収から環境に負荷のかからない状態まで処理を行い自然に還すプロセスまでを一連で学習することで、廃棄物処理施設の中で管理者としてリーダーシップを発揮するために必要な資格です。
受講資格
原則として年齢18歳以上であれば特別な受験資格はなく、産業廃棄物業界に未経験の方でも受講が可能です。そのため、新たにこの業界に参入する方や、技術管理者としてのスキルを身につけたい方にとって有益な講習です。
コースは「基礎・管理過程」と「管理過程」の2つに分かれており、学歴や廃棄物処理施設の勤務経験年数などによっては「管理過程」からの受講でよく、基準を満たしていない場合は「基礎・管理過程」からの受講となります。
※管理過程から受講するための要件
| 区分番号 | 学歴等 | 年数 |
|---|---|---|
| 1 | 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格したものに限る。) | 廃棄物処理実務経験年数不問 |
| 2 | 技術士法第2条第1項に規定する技術士(上欄「1」に該当する者を除く) | 合格後の廃棄物処理実務経験年数1年以上 |
| 3 | 廃棄物処理法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者 | 環境衛生指導員として2年 |
| 4 | 学校教育法に基づく4年制大学の理学、薬学、工学、農学の課程(相当する課程を含む)で「衛生工学または化学工学等の科目」を履修し、卒業した者 | 卒業後の廃棄物処理実務経験年数2年以上 |
| 5 | 学校教育法に基づく4年制大学の理学、薬学、工学、農学の課程(相当する課程を含む)を卒業した者で、上欄「4」に示す科目を履修しなかった者 | 卒業後の廃棄物処理実務経験年数3年以上 |
| 6 | 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校の理学、薬学、工学、農学の課程(相当する課程を含む)で「衛生工学または化学工学等の科目」を履修し、卒業した者 | 卒業後の廃棄物処理実務経験年数4年以上 |
| 7 | 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校の理学、薬学、工学、農学の課程(相当する課程を含む)を卒業した者で、上欄「6」に示す科目を履修しなかった者 | 卒業後の廃棄物処理実務経験年数5年以上 |
| 8 | 学校教育法に基づく高等学校において土木科、化学科またはこれらに相当する学科を修めて卒業した者 | 卒業後の廃棄物処理実務経験年数6年以上 |
| 9 | 学校教育法に基づく高等学校を卒業した者(大学の文系卒業者はこの区分に入ります) | 卒業後の廃棄物処理実務経験年数7年以上 |
| 10 | 学歴不問 | 廃棄物処理実務経験年数10年以上 |
| 11 | 平成4年度から平成12年度の厚生大臣指定廃棄物処理施設技術管理者講習の修了者(詳細は募集要項P7の2)をご参照ください) | |
| 12 | 平成3年度以前の厚生大臣認定廃棄物処理施設技術管理者講習の修了者(詳細は募集要項P8の3)をご参照ください) | |
講習の期間・試験内容
ここからは「基礎・管理過程」の内容について解説します。
試験の概要は以下になっております。
- 講習期間:10日間
- 合計講義時間:55時間
- 学習内容:
- 産業廃棄物処理法と関連する法律
- 各種安全管理関係
- 中間処理施設の設備構造と機能
- 廃棄物の特性と適切な処理方法
- 試験:
- 40問のマークシート方式試験
- 80%以上の正答(40問中32問正解)で認定証を取得可能
受講者の傾向
先に申し上げたように、本コースでは特に受講要件が設けられていないので、産業廃棄物中間処理施設に従事している従業員の方のみならず、以下のような様々な業界の方々も多く見られます。
- 行政関係者:産業廃棄物の許可関係を担当する役所の職員
- 工場内に処理施設を所有している製造業者:めっき業や鉄鋼業などで製造工程により廃硫酸など処理が必要な物質が発生する製造業で自社処理場にて処理を行う業者の担当者
- 水処理・浄水場の職員:産業廃棄物の管理や処理を行う施設の担当者
- 産業廃棄物処理業者:特に液体系の廃棄物(排油、排酸、排アルカリなど)を扱う事業者のうち管理を担当している責任者。または、新入社員教育として受講している職員など。
- 各種環境コンサルタント・技術者:企業向け環境コンサルタント会社の技術者や廃棄物処理施設を設計・製造するエンジニアなど
上記のように様々な業界・業種の方々が受講しますが、筆者が受講した際は行政関係者及び水処理・浄水場の職員の方々の割合が多かった印象でした。
講習で学ぶ法律
この講習では、産業廃棄物処理に関わる様々な法律について学びます。
日本国内で制定されている環境に関する法律は数百あり、それぞれが密接に関わりあって環境の保護を目指しています。また、国際的にも同じような取り組みが行われており、国際法も制定されているため、それらを講義の中で体系的に学んでいきます。以下は講習の中で取り扱われる法律の例を示しています。
- 環境基本法
- 循環型社会形成推進基本法
- 廃棄物処理法
- 資源有効利用推進法
- 容器包装リサイクル法
- 家電リサイクル法
- 建設リサイクル法
- 食品リサイクル法
- 自動車リサイクル法
- 小型家電リサイクル法
- 放射性物質汚染対策特措法
- 地球温暖化対策推進法
- オゾン層保護法
- フロン排出抑制法
- 省エネ法
- 労働安全衛生法
- 消防法
- 高圧ガス保安法
- ダイオキシン特措法(有害物質の適正管理)
- 水質汚濁防止法(水環境を守るための規制)
- その他各種、環境基準に関連する法律
実技はあるのか?
本講習は 座学のみで構成されており、実技は含まれていません。
しかし、講義の中には現場に即した内容が多く組み込まれており、各種測定器や施設のメンテナンスに関する内容であったり、テキストには載っていないような知識にわたるところまで現場での豊富な経験をもつ講師が、具体的な事例を交えて講義を行ってくれます。そのため、実務に役立つ知識を体系的に学ぶことができます。
事前に勉強しておくべきこと
原則として特別な事前学習は必要ありませんが、講習をスムーズに理解するために、事前に以下の点を整理しておくと良いでしょう。
- 自分の会社や業務で扱う産業廃棄物の種類を把握する
- 産業廃棄物処理の流れや基本的な法律について予習する
- 受講者が産業廃棄物処理施設に従事している場合は、自社工場で行われている処理工程を流れやそれぞれの意味について理解しておく。
講師が試験に出やすい重要事項を明確にして説明してくれますので、しっかりと毎日の講義を聞いて復習など怠らずに行えば初心者でも安心して学べます。
試験内容や合格率について
認定試験
講習内容をすべて受講した方のみ認定試験を受験することができます。
「基礎・管理過程」「管理過程」共通事項
- 試験は講習最終日の午後に実施
- マークシート方式
- 正答率80%以上で合格
- テキストやノートの持ち込みはできません
「基礎・管理過程」
- 試験内容は40問
- 試験時間は70分
「管理過程」
- 試験問題は20問
- 試験時間は40分
合格発表について
試験終了日から1か月以内に日本環境衛生センターから郵送にて結果が送られてきます。
合格していた場合には郵送物の中に認定証が入っています。合格点に至らなかった場合には再試験を受験できます。
受講期限は最初の受験から半年以内となっており、再試験は1回につき¥5,500(税込)が必要で2回まで受験することができます。
2回再試験を受験し合格基準に至らなかった場合には再度講習を受講する必要があります。
合格率について
主催団体からの正確なデータの公表はありません。
講習日最後の認定試験に加えて2回の再試験と合わせて3回試験を受けるチャンスがありますので合格できる可能性は高いですが、講習全体の中で重要事項と言われる重点的に勉強すべき項目が200項目以上ありますので、きちんと試験対策を行わないと合格することはできません。
筆者も講習期間中は朝、夕方の講習終了後など一日あたり1時間~2時間ほど復習の時間を設けて試験対策を行い、1度の受験で合格することができました。
技術管理者としての実務で求められる役割

技術管理者として求められる役割には、以下のようなものがあります。
- 現場の管理と指導:作業員への適切な指示と安全確保
- 法令遵守:施設が環境基準を満たしているかの確認
- 設備の改善提案:廃棄物処理の効率化や安全対策の提案
- 安全管理:従業員の健康と安全を守るための対策
この講習を受けたことで、企業の中で単なる従業員としての技術や知識だけでなく、管理者としての視点や意識が求められます。講習に送り出した企業側としてもそれを期待して講習に送り出しているはずです。
講習を受講した方からは「安全管理や法律順守の重要性についても学ぶことができるため、視野が広がった」といった声も上がっています。
まとめ
産業廃棄物処理施設技術管理者講習(中間処理施設コース)は、産業廃棄物処理業界において法令遵守、適切な処理技術、安全管理の知識を体系的に身につけることができる非常に有意義な講習です。
受講する方々には自分が働いている中間処理施設や各企業内で全体を管理する中心的な役割が求められており、そのような意識で受講することが求められます。
また、この資格を取得することで、自身が働いている企業内では技術管理者としての役割を果たすだけでなく、現場の安全性向上や業務の効率化にも貢献できるでしょう。
もちろん廃棄物処理施設以外の環境に関わる企業に勤めている方にも非常に有意義な講習です。
地球環境問題や産業廃棄物中間処理施設の処理技術などに興味のある方はぜひ受講を検討してみてください。
また、以下ページでは法律関係を始め、技術的な内容など記事をまとめたページとなっています。是非併せて確認してみてください。
株式会社オーシャンなら収集運搬から処分まで一括して対応しています
株式会社オーシャンでは「産業廃棄物処分業」の許可に加えて「産業廃棄物収集運搬業」の許可も取得しているため、回収から処分まで完結できます。排出者であるお客様は弊社までお電話をいただければ私たちが回収に伺い、積み込みから弊社作業員にて行わせていただきますので、お客様には一切お手間はいただきません。
詳しくは以下をご参照ください。