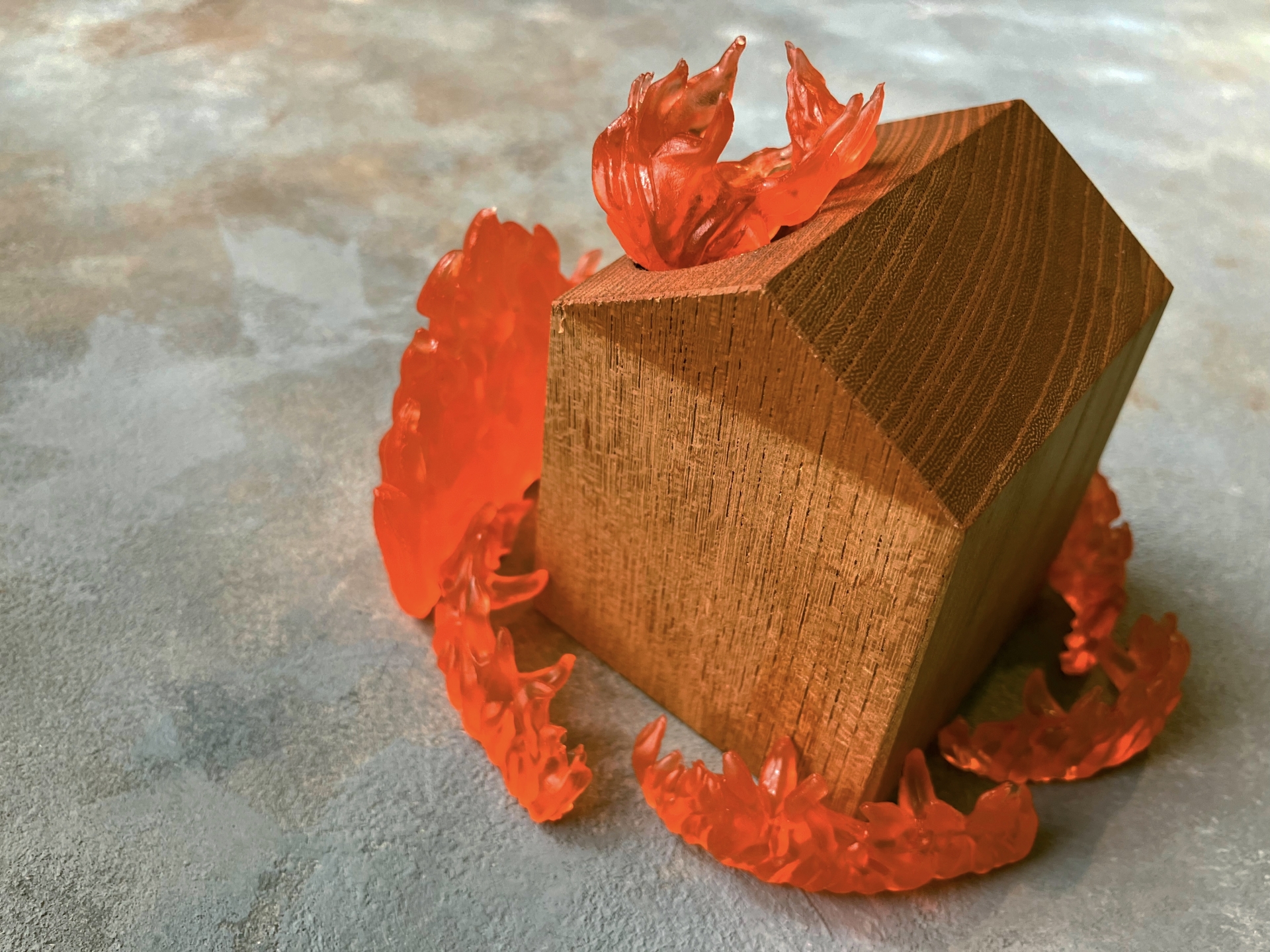廃タイヤや建設用ゴムクローラー(クローラー式建機の履帯など)は、産業廃棄物としての処理方法が定められています。(※自家用車のタイヤを自ら廃棄する場合を除く)
廃棄するにあたり、「ゴムくず」とするのか、それとも「廃プラスチック類」とするのかで処分業者の選定が大きく変わります。
特に統一の基準があるわけではなく、関東甲信越地方の事業者でも一部解釈が異なる自治体があるようです。
適切に処分を行うには「ゴムくず」なのか「廃プラスチック類」なのか、その違いを正確に理解することが不可欠です。

本記事では、法令上の基礎知識から関東甲信越の自治体別事例、実務対応の流れまでをまとめております。
本記事を読んでいただくことで法令から実務まで体系的に学ぶことができ、廃タイヤや廃ゴムクローラーを処分する際に困ることもなくなるでしょう。是非今後のバイブルとして活用してみてください。
産業廃棄物の基本区分と法令上の定義
廃プラスチック類とは
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(廃掃法施行令) 第2条第12号では、以下のように定義されています。
合成樹脂、合成ゴム、その他の合成高分子化合物を主成分とする廃棄物を「廃プラスチック類」とする。
業界では略して「廃プラ」と呼ばれることが多く、廃タイヤもこの「廃プラスチック類」に含まれるのが一般的な整理です。
ただし、自治体によっては「ゴムくず」として扱う場合もあるため、各自治体の区分を確認することが重要です。
ゴムくずとは
産業廃棄物区分のひとつに「ゴムくず」があります。
その定義は「天然ゴムを原料とするもの」に限られており、具体的には以下のように整理されています。
天然ゴムくず(生ゴムや天然ゴム製品由来)を指し、合成ゴム(廃タイヤ等)は含まない。
つまり、「ゴムくず」に該当するのは天然ゴム由来の廃棄物であり、合成ゴム製品(廃タイヤやゴムクローラーなど)は「廃プラスチック類」に分類されます。
廃タイヤがどちらにも該当する背景
かつてのタイヤには天然ゴムのみで製造されたものもあり、その場合「ゴムくず」として整理できる余地がありました。
しかし現在のタイヤやゴムクローラーは、天然ゴムと合成ゴムを組み合わせたハイブリッド製品がほとんどです。
そのため、法令上は理論的に「ゴムくず」にも「廃プラスチック類」にも該当し得るものの、実務上は「廃プラスチック類」として取り扱うのが標準的な整理となっています。
実際、日本自動車タイヤ協会(JATMA)のガイドラインでも、廃タイヤは「廃プラスチック類」と明記されています。
廃タイヤ・ゴムクローラーの区分が重要な理由
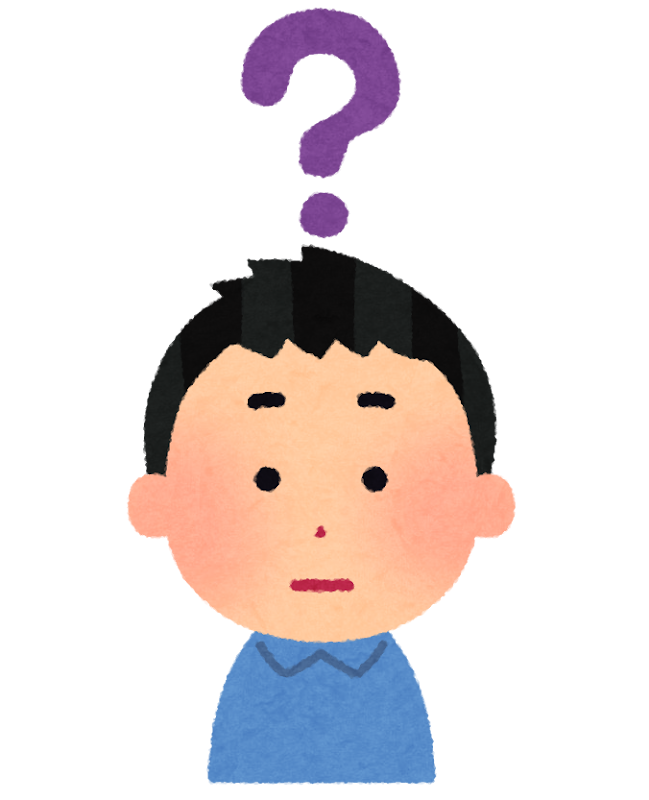
許可品目と処理業者の選定
廃棄物処理を委託する際には、必ず「産業廃棄物処理業の許可」を持つ事業者に依頼することが法律で定められています。
業者の許可証には、処理可能な品目として「ゴムくず」や「廃プラスチック類」などが明記されています。
廃タイヤや廃ゴムクローラーの処分を取り扱う多くの業者は「廃プラスチック類」の許可を取得しており、「ゴムくず」のみの許可では引き取りを断られるケースがあります。
したがって、処理を依頼する際には必ず以下を確認することが重要です。
- 収集運搬業許可証の「許可品目」に「廃プラスチック類」が含まれているか
- 処分業許可証でも「廃プラスチック類」の取り扱いがあるか
この確認を怠ると、委託契約が無効になったり、不法投棄リスクにつながる恐れがあります。
マニフェスト・契約時の注意点
産業廃棄物の処理を委託する際に、許可品目と異なる区分で依頼すると、法的なトラブルや処理拒否、さらには追加費用の発生につながるリスクがあります。
特に注意が必要なのは、以下の2点です。
- 契約書の記載内容
委託契約書には、廃棄物の品目を「廃プラスチック類」や「ゴムくず」など正しく記載する必要があります。許可証にない品目を契約書に記載した場合、契約そのものが無効とみなされる可能性があります。 - マニフェストの整合性
マニフェストには、実際に排出した廃棄物の品目を記載します。現物(廃タイヤ等)の性状と、契約書・許可証に記載された品目が一致していなければ、法令違反となる恐れがあります。
つまり、「現物 → 契約書 → 許可証 → マニフェスト」の4つが一致していることが必須です。
これを徹底することで、法的リスクを回避し、トラブルのない委託処理が可能になります。
安全・リスク管理(火災など)
廃タイヤやゴムクローラーは、燃えにくいイメージがありますが、実際には火災リスクが高い廃棄物のひとつです。
特にゴムクローラーは不飽和結合を含む化学構造を持ち、酸化によって熱を帯びやすく、条件によっては自然発火に至る可能性があります。実際に、全国の処理施設やストックヤードで火災事故が発生しており、安全管理が強く求められています。
そのため、以下の点が重要です。
- 保管時は直射日光・高温多湿を避け、通気性を確保する
- 大量保管する場合は、消防法や自治体指導に基づき区画整理を行う
- 運搬時は荷崩れ防止や摩擦防止に留意する
- 処理業者は防火設備や監視体制を整えているかを確認する
こうした管理を徹底することで、火災や二次災害のリスクを抑え、安全な処理を行うことができます。
以下の記事で火災のリスクや対応策についてまとめてあります。
関東甲信越地方における自治体の区分事例(リンク付き)
本節では、関東甲信越(1都9県)の自治体で「廃タイヤ」や「ゴムクローラー」の区分について明記している公式情報をご紹介します。
東京都
東京都環境局の公式サイト「産業廃棄物の具体例」では、「合成ゴム(廃タイヤ)は廃プラスチック類に分類」と明記されています。
また、東京23区などで活用される条例資料やハンドブックにも同様の記載があるため、東京都内では「廃プラスチック類」として取り扱うのが標準です。
出典:一般廃棄物処理業の手引き(東京二十三区清掃協議会)
神奈川県(相模原市など)
相模原市の公式ページでは、「廃プラスチック類」の品目に廃タイヤが含まれることが明記されています。一方で、「ゴムくず」は天然ゴムくずのみを指すと定義されています。
出典:産業廃棄物(相模原市HP)
また、神奈川県全体の資料「かながわの産業廃棄物(PDF)」でも、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)は廃プラスチック類に分類されると整理されています。
千葉県
千葉県が公開している「産業廃棄物のパンフレット(PDF)」では、廃プラスチック類の具体例として廃タイヤが記載されています。
このことから、千葉県では廃タイヤやゴムクローラーを「廃プラスチック類」として扱うことが明確に示されています。
埼玉県・埼玉市
埼玉県内の許可業者の許可票を確認すると、「廃プラスチック類」「ゴムくず」「金属くず」など、複数の品目を取得しているケースが多く見られます。
一方で、埼玉県が公表している「産業廃棄物の取扱いについて(PDF)」では、廃タイヤは「廃プラスチック類」に分類されると明記されています。
このため、実務上も埼玉県では「廃プラスチック類」として処理・契約を行うのが基本的な整理といえます。
茨城県
茨城県が公表している廃棄物統計や各市町村の産業廃棄物区分において、廃タイヤは廃プラスチック類として整理・統計化されています。
例えば水戸市の公式サイトでも、廃タイヤは「廃プラスチック類」に含まれると記載されており、県内の取扱いは統一されています。
出典:産業廃棄物の区分(水戸市HP)
栃木県
栃木県が公表している「産業廃棄物の種類ごとの集計単位と重量換算係数(PDF)」では、「廃プラスチック類(廃タイヤ)」と明記されています。
このことから、栃木県でも廃タイヤは「廃プラスチック類」として統計・処理されることが確認できます。
群馬県
群馬県や高崎市の公式資料においても、廃タイヤは「廃プラスチック類」に含まれることが明記されています。県の統計や分類表でも、廃タイヤは廃プラスチック類として整理されています。
山梨県
山梨県が公表している「平成21年度 山梨県産業廃棄物実態調査報告書(PDF)」において、廃プラスチック類の具体例として廃タイヤが記載されています。
このことから、山梨県でも廃タイヤは「廃プラスチック類」として整理されており、統計上もその区分で取り扱われています。
長野県・長野市
長野市の公式サイト「産業廃棄物の区分」では、「廃プラスチック類(合成ゴムくず・廃タイヤを含む)」 と明記されています。
このため、長野市を含む長野県内では、廃タイヤは一貫して「廃プラスチック類」として扱われることが確認できます。
新潟県・新潟市など
新潟県および新潟市の公式資料でも、「廃プラスチック類として廃タイヤを含む」ことが明記されており、県・市ともに一貫した整理がされています。
(出典:新潟県「産業廃棄物の区分」)
廃タイヤ・ゴムクローラーを「ゴムくず」として処理できる?実務的判断基準まとめ
| 判定項目 | 「ゴムくず」として可能か? | コメント |
|---|---|---|
| 材料組成(天然ゴム主体かどうか) | 可能性あり | 天然ゴム100%なら法令上は「ゴムくず」と整理可能。ただし現代の廃タイヤ・ゴムクローラーはほぼ合成ゴムが混在しています。 |
| 自治体の公式分類 | 現状、ほぼ“廃プラスチック類” | 関東甲信越の自治体では、公式資料のほぼ全てで「廃プラスチック類」と明記。ゴムくず対応は未確認。 |
| 委託先の許可品目 | 要確認 | 多くの処理業者は「廃プラスチック類」の許可を取得。ゴムくずのみの許可では対応できない場合があるため、許可票で必ず確認が必要。 |
| 処理コスト・手間 | 廃プラスチック類が現実的 | ゴムくずのみ扱える業者は少なく、相場も不明確。廃プラスチック類で処理する方が現実的かつコスト面でも有利。 |
まとめ:今すぐ使える「区分判断チェックシート」
廃タイヤやゴムクローラーの処理にあたっては、以下のステップを押さえることで、法令違反や契約トラブルを防ぐことができます。
1. 自治体の公式区分を確認する
- 自分の地域の自治体公式ページで「廃タイヤ」の区分を確認する
- 関東甲信越では 「廃プラスチック類」が主流
2. 処理業者の許可票を確認する
- 「廃プラスチック類」「ゴムくず」など、どの品目を扱えるかを必ず確認
- 両方取得している業者でも、実際にタイヤ・ゴムクローラーを扱うかは要確認
3. 契約書・マニフェストの整合性を確認する
- 処理品目を契約書・マニフェストに明確に記載
- 許可証・現物・契約書・マニフェストの区分が一致しているか必ず確認
4. 自治体へ確認・問い合わせ
- 不明点がある場合は、処理業者任せにせず 自治体の環境部局へ問い合わせ
- 公式回答を得ておくとトラブル防止につながる
以下ページでは法律関係を始め、技術的な内容など記事をまとめたページとなっています。是非併せて確認してみてください。
よくある質問(FAQ)
法令上可能でも、関東甲信越では明記例はほとんどなく、実務上は「廃プラスチック類」が主流。
天然ゴム主体であれば「ゴムくず」に該当する可能性あり。ただし自治体と処理業者への確認が必要。
マニフェストには一つの品目を記載するのが基本です。混合の場合は「混合廃棄物」として相談してください。
株式会社オーシャンなら収集運搬から処分まで一括して対応しています
株式会社オーシャンでは「産業廃棄物処分業」の許可に加えて「産業廃棄物収集運搬業」の許可も取得しているため、回収から処分まで完結できます。排出者であるお客様は弊社までお電話をいただければ私たちが回収に伺い、積み込みから弊社作業員にて行わせていただきますので、お客様には一切お手間はいただきません。
詳しくは以下をご参照ください。